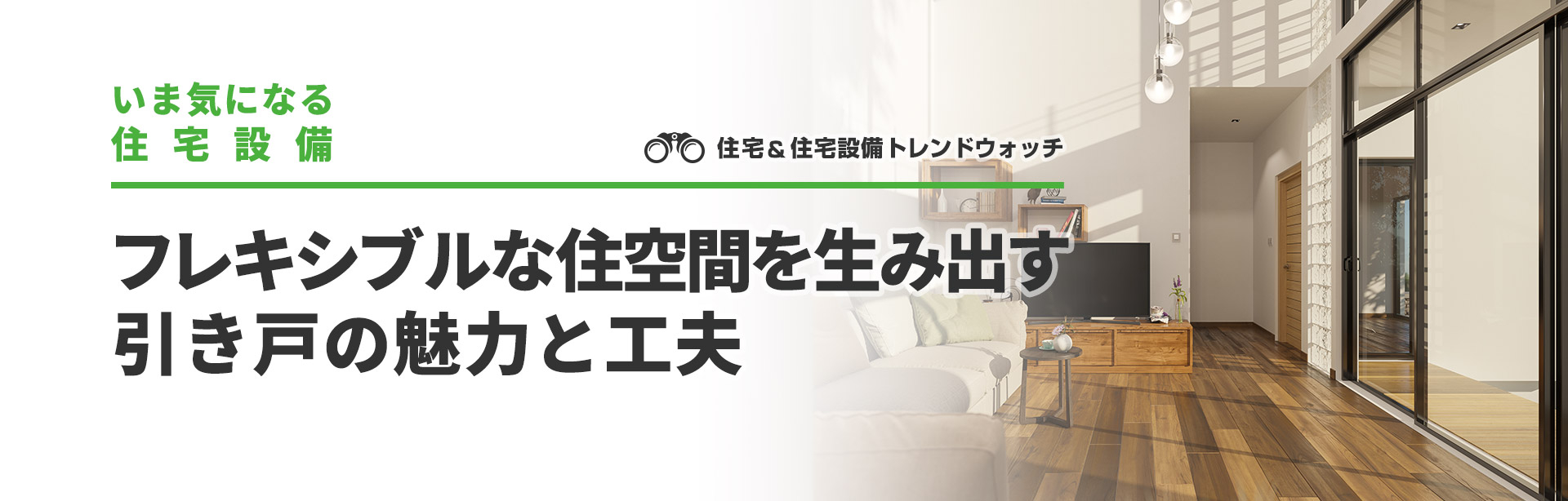大開口で風通しの良い空間を作る

引き戸は日本発祥の建具で、その始まりは平安時代に遡るといわれています。現代まで、様々に形を変えて普及してきたことには理由が沢山ありますが、高温多湿な日本の風土の影響は特に大きいと思います。徒然草に「家の作りやうは、夏をむねとすべし」とあるように、蒸し暑い夏を快適に過ごす為、風通しが良いことは日本の住空間では重要なこと。広い開口部をもち、必要に応じて外すこともできる引き戸は、板戸、障子、襖など、様々な形で風と光を入れ、室内を開放的にしてきました。
私の自宅では内外を仕切る窓のほとんど、家の内部の間仕切りも、気が付けば全て引き戸です。日本発祥の伝統を受け継ぎ、その利点を生かした現代の住空間での使い方を、我が家を事例として、一部ご紹介したいと思います。
出入口であり壁でもある
引き戸は、開き戸のように開閉の際に戸が動くためのスペースを必要としません。開き戸のように前に人がいて、開けた時にぶつかってしまう、ということもありません。出入口のキワまで、スペースを最大限に有効活用できます。写真のように、上吊式とすることで床に何もアクセントがなく、引き手をフラットに納めて壁厚の中に戸が全て収まり、まるで建具が何も無いかのようにすることもできます。
開口部でもあり壁でもある。存在を消すことのできる引き戸で空間を仕切ることで、部屋と部屋が一体的につながり、家全体に広がりが生まれます。


ソフトクローズ式で、動きも大変軽く滑らか。
引き戸で部屋を増やす
写真は、襖のように部屋を分割するための木製引き戸です。リビングとダイニングの間は、通常は何もなく一続きの空間なのですが、ゲストの泊まる部屋が足りないという時など、仕切ることで部屋を増やすことができるようにしました。普段は壁内に格納されている1枚、壁に同化させている2枚、トイレの前に屏風状に目隠しの役割を持たせた2枚、合計5枚の引き戸を動かすことで、部屋がもう一つ出来上がります。
床から天井までのかなり背の高い大きい戸であり、壁としての安定性も必要なため、ここでは上吊式ではなく、床に埋め込んだレールをガイドに、戸車で動くようにしています。また、引き戸の表面に黒板塗装を施してある為、大きな黒板としても使えます。


建具は、建築の中で唯一動くものだから面白い
共に事務所を営んでいる主人曰く、「建具というのは、建築の中で唯一動くものなのだよ。だから面白い。」
引き戸だけでなく、開き戸、折れ戸、障子、襖、広くはパーティション、ルーバーなど、空間を間仕切る装置である建具。デザインの要でもあり、動くことでフレキシブルな空間を生み居心地の良さもコントロールする、重要な役割を担う建築の構成物です。
日々進化する建具金物なども取り入れながら、オリジナルな工夫を重ねディテールを洗練させていくことが、建築の質を高めることに繋がると考えています。
テキスト=八木このみ(八木建築研究所)
監修=リビングデザインセンターOZONE